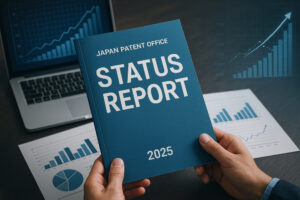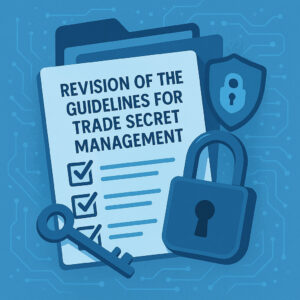特許出願や商標登録出願では、出願後に(特に、拒絶理由通知に対する応答の際に)補正を行うことがありますが、その補正内容によっては、追加の庁費用(特許庁手数料)が発生する場合があります。
本記事では、実務上見落とされやすい「補正に伴う追加手数料」における特許出願と商標登録出願の違いについて簡単に説明いたします。
特許出願における請求項数の増減
特許出願の場合、出願審査請求料は、審査請求時の請求項数に基づいて算定されます。通常出願又はPCT出願の国内移行に応じて計算式が以下のように異なります。
| 項目 | 計算式 |
|---|---|
| 出願審査請求料(通常出願) | 138,000円+(請求項の数×4,000円 |
| 出願審査請求料(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 83,000円+(請求項の数×2,400円) |
| 出願審査請求料(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 124,000円+(請求項の数×3,600円) |
審査請求後に手続補正書を提出して請求項を追加した場合には、審査請求時から増加した請求項数に応じた追加手数料を特許庁に納付する必要があります。
例えば、通常出願において、拒絶理由に対する応答として新規従属項を2つ追加した場合、8000円(=4000円×2)の追加手数料を特許庁に納付する必要があります。一方、請求項の数を減らした場合では、既に支払済みの審査請求料が返還されることはありません。削除した請求項も既に審査対象となっているためです。
商標登録出願における区分数の増減
商標登録出願では、出願時の区分数に基づいて出願料が算定されます。
商標登録出願:3,400円+(区分数×8,600円)
商標登録出願では、出願後に指定商品・役務や区分を追加することは要旨の変更となるため難しいのですが、拒絶理由通知書において商標法第6条第2項に係る拒絶理由(区分相違)を指摘された場合には区分を増加する補正を行うことがあります。
例えば、本来であれば30類に属する指定商品を29類の指定商品として記載した場合には、区分相違に係る拒絶理由が指摘されます。この場合、補正によって区分を増加すると追加の庁手数料(1区分あたり8,600円)が必要となります。
ここで、特に注意が必要なのは、当初の区分を削除して別の区分を追加する場合です。
例えば、出願時の区分が29類、35類の2区分であって、拒絶理由通知において29類の指定商品の一つを30類の指定商品にすべきであると指摘された場合を想定します。
本ケースにおいて、出願人が35類を削除しつつ、30類を新たに追加した場合には、補正後の区分数と出願時の区分数は共に2つとなります。
| 補正前 | 補正後 |
|---|---|
| 29類、35類 | 29類、30類 (35類は削除) |
しかしながら、このような場合でも、区分の削除と追加は互いに相殺されず、30類の追加に伴う追加手数料8600円が発生する場合があります。追加手数料を納付しない場合、手続補正指令(方式)が出されます。
この点について審査官に以前確認したことがありますが、35類の指定役務については既に審査済みとなっているため、補正前後で区分数が変わらない場合であっても追加手数料の支払いは必要とのことでした。
まとめ
今回は特許出願と商標登録出願における補正に伴う追加庁手数料の取り扱いの相違について説明いたしました。
特許出願では、審査請求時の請求項数に対して補正後の請求項数が増加した場合にのみ追加の庁手数料が発生します。一方、商標登録出願では、補正前後で区分数が変わらない場合であっても追加手数料が発生する場合があります。
このように、特許出願と商標登録出願では追加手数料に関する取扱いが若干異なる点に注意が必要となります。