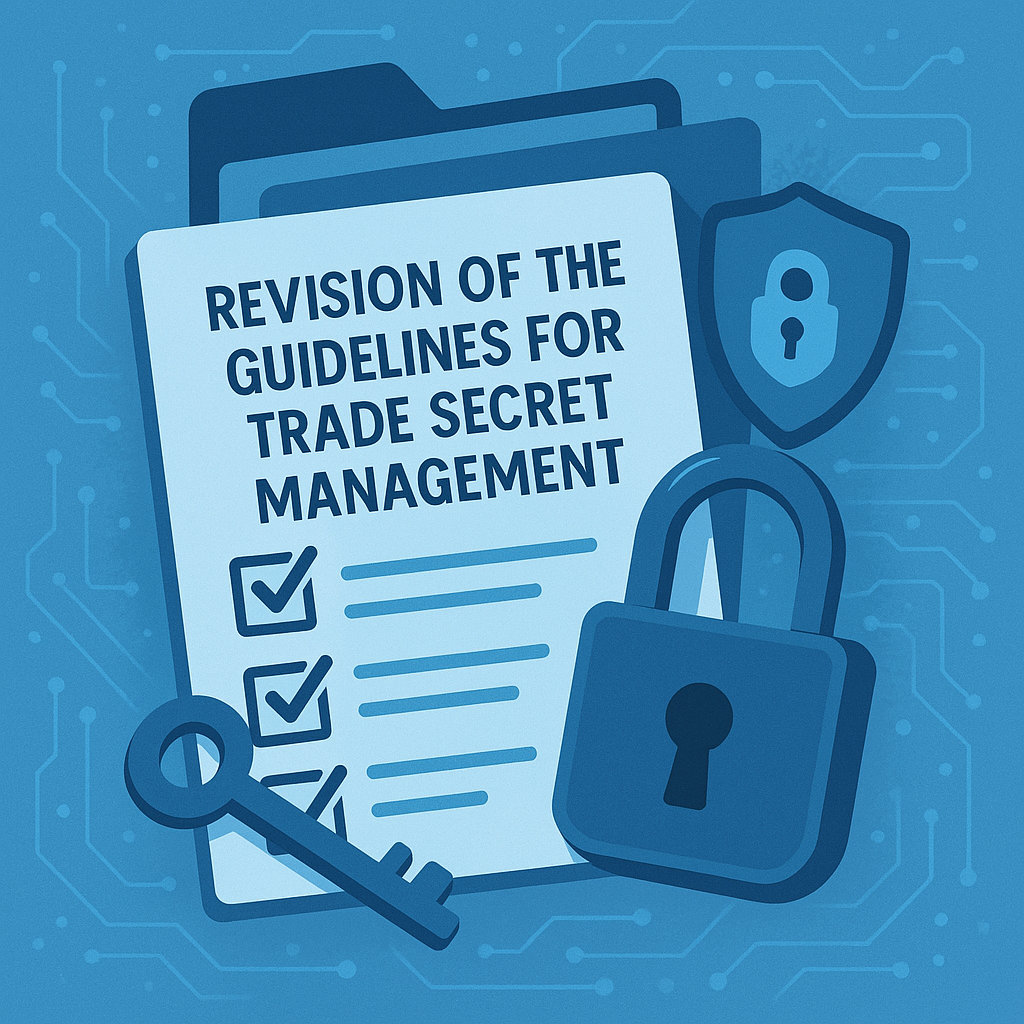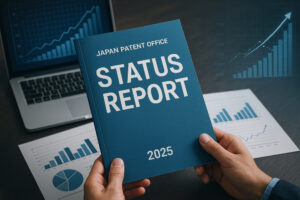営業秘密管理指針の改訂版が令和7年3月31日に公表されました。
営業秘密管理指針は、営業秘密の法的要件を理解する上で、重要な資料となります。特に、営業秘密管理指針は、不正競争防止法により営業秘密として法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとなります。
今回の改訂内容では、平成31年以降の裁判例(民事・刑事)が多く例示されております。
また、本改訂版では、一般情報に対する営業秘密の「合理的区分」の措置に関する一連の記載が削除されるとともに、当該記載は「秘密管理措置の程度」に関するセクションにおいて追記されております(※「合理的区分」に関しては、札幌高裁(R5.7.6)の判決等において注目されておりました)。
営業秘密の重要な要件である秘密管理性を満たすための秘密管理措置の程度について以下が列挙されております(10頁参照)。
- 媒体の選択や当該媒体へ表示
- 媒体に接触する者の限定
- 営業秘密と他の情報との分別管理(※合理的区分)
- 営業秘密たる情報の種類・類型のリスト化
- 就業規則や秘密保持契約(あるいは誓約書)などの規程等において守秘義務を明らかにする
- 従業員への研修・啓発
さらに、改訂内容では、生成AIと秘密管理性の考え方についての一例が紹介されています。
次に、有用性の考え方としては主に以下2点が明記されております。
- 情報が公序良俗に反するなど保護の相当性を欠くような場合でない限り有用性の要件は充足される。
- 有用性の要件の判断に際しては、当該情報を取得した者がそれを有効に活用できるかどうかにより左右されない。
非公知性の考え方としては主に以下4点が明記されております。
- 第三者からのハッキング等により営業秘密がダークウェーブに公表されたとしても、その一事をもって直ちに非公知性が喪失するわけではない。
- 営業秘密が公知情報の組み合わせであって、その組み合わせが知られていたり容易であったとしても、取得に要する時間や資金的コストがかかるため財産的価値があるという場合に非公知と言いうる。
- 進歩性(特許法第29条第2項)との関係において、当該情報が非公知の情報といえるための要件として「予想外の特別に優れた作用効果」を生じさせるものであることまでは要しない。
- リバースエンジニアリングによって営業秘密を抽出できる場合、抽出可能性の難易度の差によって判断がわかれる。
まとめ
筆者が2023-2024年度の日本弁理士会の不正競争防止法委員会において、営業秘密の判例調査・研究をしていた経験上、2019年以降の営業秘密に関する民事事件の認容率はかなり低いことが判明しております。今回の営業秘密管理指針の改訂を受けて、今後の営業秘密(特に、秘密管理性)に関する裁判所の判断がどう変わっていくか注目していきたいと思います。